営業時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
小さい企業だと簡単に考えると大変なことに!
1 このような就業規則の考えはないでしょうか?

御社では、次のような考えが過ったことはないでしょうか?
⓵規模が小さいから、就業規則はモデルやひな型で間に合う?
⓶就業規則は、労働時間、休み、給料、服務規定、解雇規定ぐらいがあれば十分だ?
⓷別規程は大企業が必要とするものでしょ?
⓸細かい規定じゃ、よくわからないし・・・?
⓹立派な規定にしなくても、内の従業員は特に問題ないよ?
これらは、ほんの一部ですが、これまで就業規則の作成・変更のお手伝いをさせていただいたお客様から届けられた声です。これらの考えで就業規則をやるとどうなるでしょうか?
目の前に出来事が起きていないと、ふと安易な思考になりがちです。
当事務所では、これまで数ページの就業規則やあいまい規定の条文、規定のない就業規則など数々の不備を目にしてきました。
ほんのさわりをこのページでご紹介しておきたいと思います。
1 小さい会社だと就業規則を簡単に規定したら・・
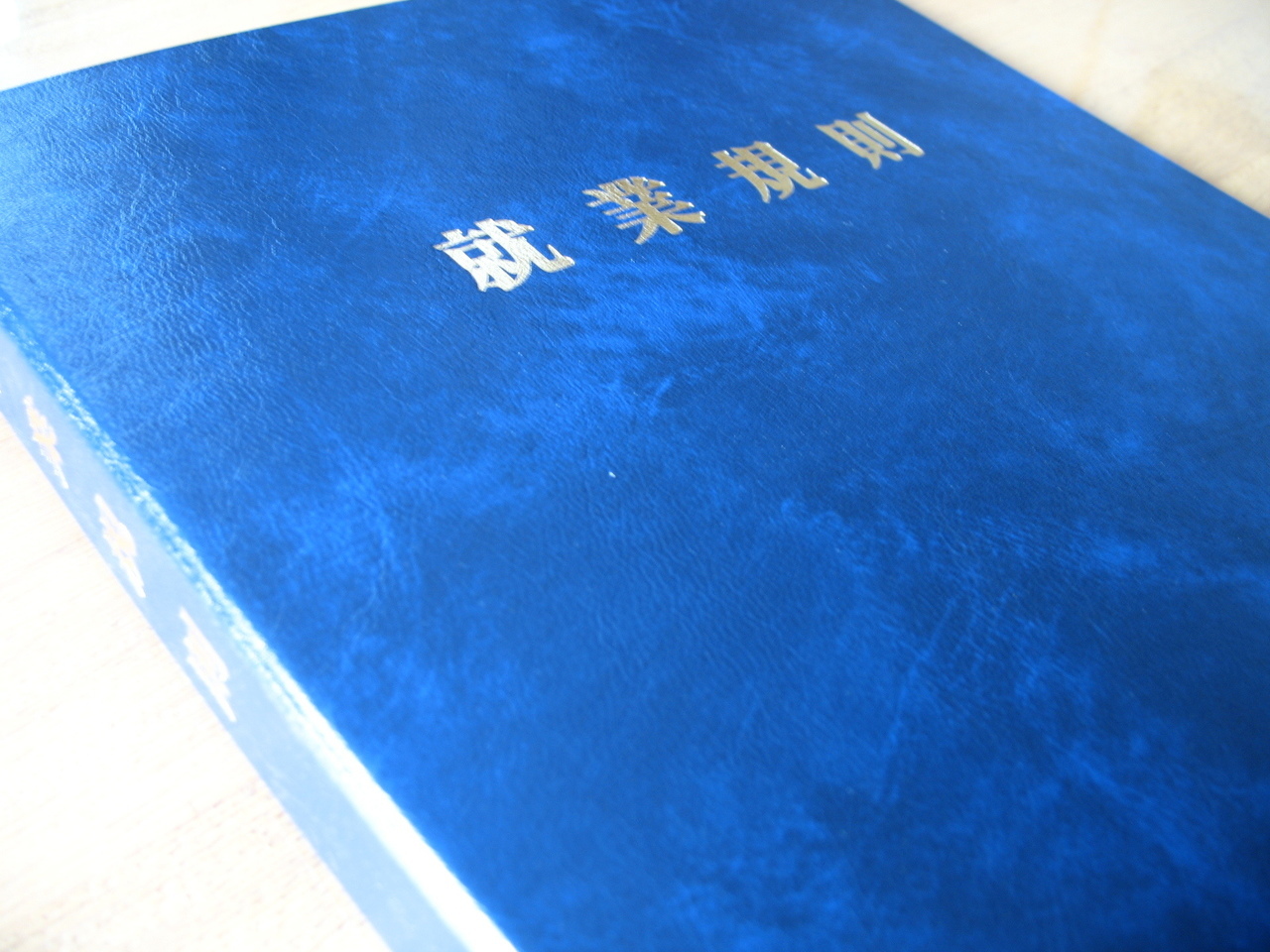
たとえば、以下の病気休職の例で考えてみましょう!
越谷保険事務所では、従業員Pが病気による体調不良で休みに入りました。社長は、人手が必要な時にと困りました。
「いったいいつまで休み気なのかなあ」と終わりが見えません。就業規則には、病気欠勤が3か月間に30日以上に達した場合には、休職命令を出すと規定しています。
Pさんは、連続して1か月以上休んだので、社長は、休職命令を出しました。休職期間は6か月です。6か月で復職できなければ退職です。
3か月休職したところで、Pさんは、医師の診断書を題してきました。これまでも診断書は出しています。そこには、「軽業務ならば就労可能」とありました。
Pさんから、医師の診断書の通り、働けますので、仕事に就かせてくださいと希望がありました。しかし、社長は、「軽業務じゃだめだ。本来の業務ができないじゃないか」「しばらく休職として扱う」としました。
Pさんは納得しません。医師が働けると言っているのに、働かせないなんて契約違反だと言ってきました。社長は、これ以上、どうしていいかわかりません。
さて、越谷保険事務所の何が困惑させる要因になったのでしょうか?ここが、対策すべき個所だったのです。
2 就業規則に規定がないとトラブルが解決できない
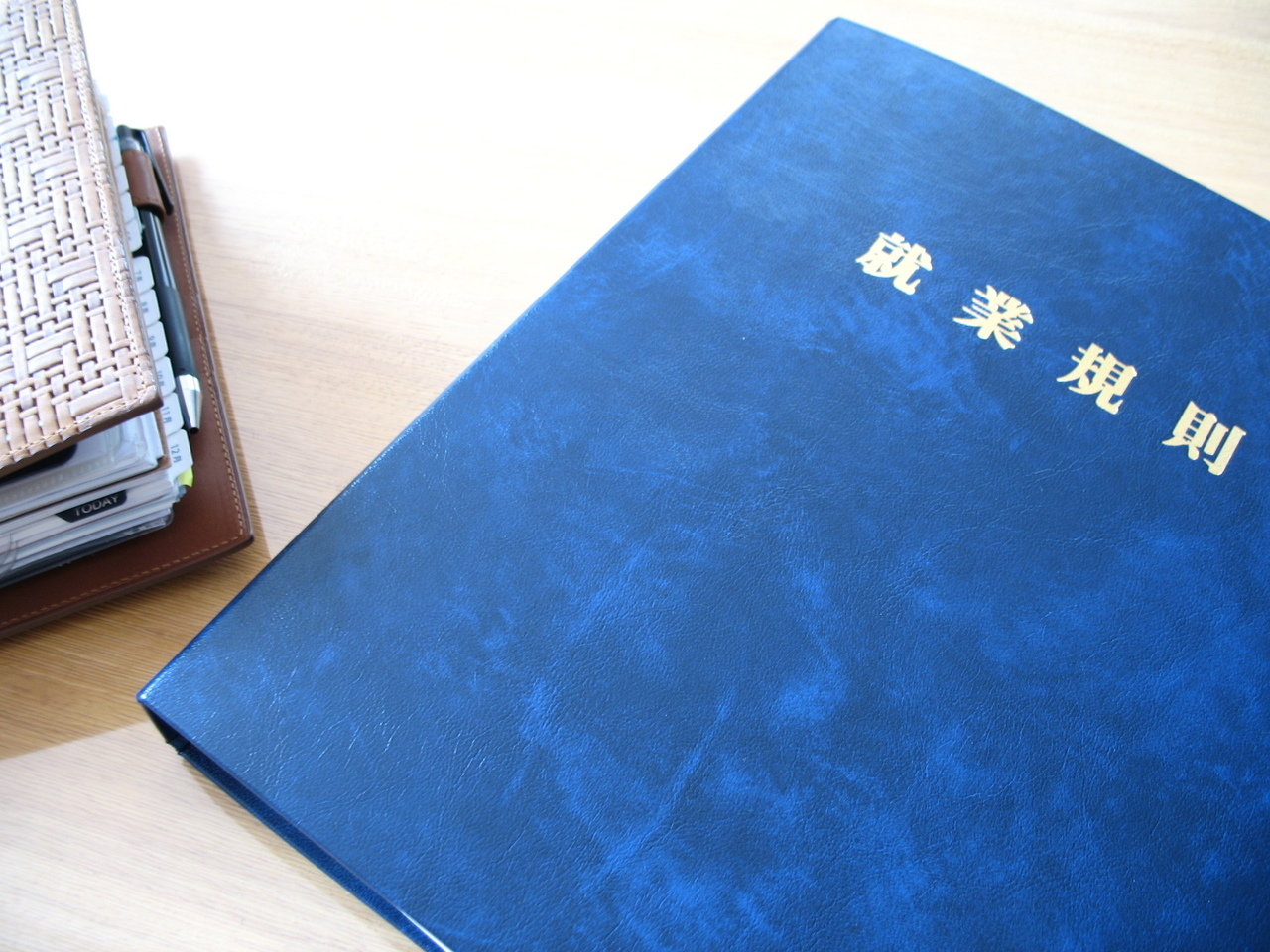
従業員Pに対し、社長は引き続き休職を命じました。その後の診断書でも「軽業務ならできる」旨は変わりませんでした。
6か月の休職期間満了日が来て、社長は休職事由が解消されないためとして解雇しました。
Pさんは、「社長、酷いですよ。一方的に。出勤できますよ。」と懸命に伝えた。社長は「普通に働けるのか?」と聞きました。Sさんは「わかりません」というため、社長は、「そんな、当てにならない、体調不良の欠勤をいつまでもさせておくわけいかないだろ。頭冷やせ。もう来なくていい」と言ってしまいました。
数日後、労働局から指導の連絡ですけどと電話が入り、「解雇は難しいですよ。どのくらいの業務ならできるのか確認してませんよね。その場合、どういう状態になったら復職のできるのか、要件は決まっていますか?」と社長は踏んだり蹴ったりだった。Pさんが労働局に相談申告したものだった。
社長は、しどろもどろになっていたが、もう、解雇したから放っておきました。忘れかけていた2か月後に、労働局から、「あっせん申請書」が送られてきました。行政機関から来る封筒にいいものは入っているはずはないが、社長は、「まさか、あっせん申請書とは。どうしたらいいんだろう」と戸惑うことになりました。
越谷保険事務所の就業規則には、多くの取り決めが欠けていました。どうなったら、復職できるのか、主治医の見解だけで決めるのか、他の医師への受診協力を求めるのか、どちらも見解が違った場合は、どうやって決定するのか、などなど他にもまだまだあります。
就業規則をモデル版やひな型で運用した場合、最低限のことしか規定がないので、越谷保険事務所では、まったく対応できませんでした。
どのようなことが起きる可能性があるかを想定し、就業規則で対策しておくことが大切です。この点が欠けたために今回のように苦労することになりました。
休職期間満了をめぐるトラブルですから、解雇問題がついてきます。解雇理由の規定にも大きな影響が及びます。
どうですか?これはほんの一例で、ここでは、休職の話題を取り上げましたが、配置転換、労働時間、残業、車両運転などなど、同じように、想定して防止策を規定しておくことが必要です。
これがオリジナルの就業規則になります。肝心な規定がない就業規則では、トラブルに対応できませんし、解決は難しくなります。
他にも、就業規則の適用の範囲、種々の定義、採用に関する規定、試用期間に関する規定、服務規定、労働時間の規定、年次有給休暇の規定、解雇規定、懲戒処分の規定、損害賠償の規定、競業避止義務規定、健康診断の規定、定年・雇用継続などの規定、そのほか福利厚生の規定、給与に関する規定など、できるだけあてはめが可能となるように、実態と将来の状況を加味してきめ細かく規定する必要があります。
既製品の就業規則は、その規則の規定そのものが、御社の発想で検討して作ったものではありませんので、使いやすくはありません。「使いやすい」とは、条項のあてはめやすさなど運用しやすいか、正しく運用できるベースになり得るかという問題です。
簡易版の就業規則では、、必要な条項がなかったり、なくてもいい条項やあってはならない条項があったり、条項の内容が甘かったりと不都合な条項、内容的にも不合理な条項も混在しています。つまり、スムーズに労務実務にあてはめることができない規定で構成されてしまっています。
御社に就業規則がある場合には、当事務所に作成を依頼されますと、原型をとどめていない別物の就業規則に変身しているはずです。中味が違います。
なかなかピンとこないかと思いますで、ぜひ、一度、ご相談いただければと思います。
ぜひ、運用とリスクに対策できる経営のための就業規則を整備しましょう!
簡易版就業規則の特徴

最後に、一般的なカニ版の就業規則の特徴を挙げておきます。すべてではりませんが、傾向としてはこうですよというものです。
- 全体の条文数が少なくなる。条文記述の内容がシンプル化されるため、労務リスク対応の程度がかなり低くなってしまう。
- お客様独自の各種対策に関する規定が薄くなる傾向にある。
- 服務規定や遵守規定などお客様独自の要素が求められる部分の規定内容が不十分なものになる可能性が高い。
- パワハラなどハラスメント関連規定も、最低限の規定にとどまる可能性がある。
- 解雇・退職、配置転換、休職などの規定、休日、労働時間などの目委員条項も最低限の内容になりがちになる。
- 全体の条文内容があっさりしている。
- 適用範囲・各種定義がアバウトになっている。 ・・etc・・・・・
お気軽にお問合せください

お電話での相談お申込み・お問合せ(社労士直通へ)
平日の9時から18時
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
※営業のお電話・メールはお断りさせていただいております。
サイドメニュー
お役立ち情報のご案内





